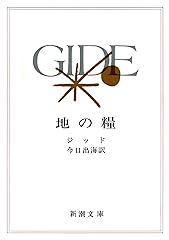町を書物のように読んでみよう
劇作家・寺山修司の有名な言葉に「書を捨てよ、町へ出よう」というものがある。 1967年に出版された評論集のタイトルにもなっており、さらにはそれを下敷にして舞台化・映画化もされている。
さて、この言葉は「町を書物のように読んでみよう」と続くのだ、という主張をどこかで見かけたような気がしているのだが、これがいくら探しても見つからない。寺山の評論集にはそんな言葉は書かれていないし、舞台版および映画版のシナリオを取り寄せて確認してみたがそちらにも見当たらない。検索エンジンで探してみると、かつて自分が書いた同じ疑問についての記事のみがヒットする始末である。生成AI に尋ねてみてもトンチンカンな回答しか返ってこない。
ということで気になりつつも出自不明のため、この言葉を使うのはためらわれるのだが、「書を捨てよ、町へ出よう。町を書物のように読んでみよう」と続けて読むとおさまりがよく、含蓄もある。
YouTube でときおり見かけるコメントで、「あまりによく出来ているので、私がこれを作った、ということにできないか」という、ちょっとヒネった賞賛をしているものがあるが、それと同じ気持ちで、この「町を書物のように読んでみよう」という言葉、私が考えた、ということにならないだろうか。
冗談はさておき、少し粘って探していたら、藤本智成による紀要論文「『地の糧』を読む寺山修司」1に、寺山の言葉についての詳細な解説が書かれていた。それをヒントに探してみたところ、寺山の別の評論集『青蛾館』に所収の「書物という虚構」2という評論に、以下の一節があることがわかった。
たとえば書物とは『印刷物』ばかりを意味するものではなかった。街自体が、開かれた大書物であり、そこには書きこむべき余白が無限に存在していたのだ。
かつて、私は『書を捨てよ町へ出よう』と書いたが、それは『印刷物を捨てよそして町という名の、べつの書物を読みに出よう』と書き改められなければならないだろう。 (強調筆者)
これは私が探していた言葉にかなり近いが、表現が少し違う。藤本の論文を頼りに他にもいろいろあたってみたものの、これ以上に近い表現は見つけられなかった。
真相はいまだに分からないが、先述の寺山の文章を誰かが雑誌記事だか文庫本の解説だかで紹介する際に、少し表現を変えて書いてしまったのを私が見かけた、といったあたりではないだろうか。
それから、君はすっかり読んでしまったら、この本を捨ててくれ給え——そして外へ出給え。私はこの本が君に出かけたいという望みを起さしてくれるように願っている。どこからでもかまわない。君の街から、君の家庭から、君の書斎から、君の思想から出てゆくことだ。私の本を携えて行ってはいけない。 (今日出海訳)(強調筆者)
寺山は『地の糧』のこの一節に強く影響を受けたようで、何度も評論や随筆で引用していることが藤本論文で指摘されている。
ただ、よく読むとジッドの書いていることは、寺山のそれとは少し異なる。寺山は本を捨てて町へと出向くことを促しているが、ジッドは「街から…出てゆ」け、と書いている。
同書の1927年版に著者自らによって付された序によれば、本書は「無一物 (“dénuement”) に対する弁明」であるという。書を捨て、街を捨て、何者にも束縛されない境地へと脱出せよ、というのが『地の糧』の目指す地点だとするならば、寺山の「書を捨てよ、町へ出よう」およびその続きとしての「町という名の、べつの書物を読みに出よう」は、書物を読むのと同質の楽しさを町の中に見出そうとする姿勢である。それは、劇場を飛び出して街中で演劇を行ったり、競馬場やバーでの出来事を評論に書き記し続けた寺山の活動と、よく呼応する。
ちなみに、寺山による『地の糧』からの引用は安定しない。藤本論文にまとめられている引用文を、発表順に並べ直してみる。
「ナタナエルよ,書を捨てよ,野へ出よう」という一句が,ぼくを喜ばした.(「カルネ」(1956))
——「ナタナエルよ,書を捨てよ.外へ出よう」ってやつか.(『ひとりぼっちのあなたに』(1965))
これらは「町」が登場しない。これが、
直接のコミュニケーションによる詩を見出そうとしたら,私たちは「書を捨てて,町に出る」しかないような気さえするのだ。(『戦後詩 ユリシーズの不在』(1965))
ナタナエルよ,書を捨てよ.町へ出ようではないか(『時代の射手』(1967))
となると、出ていく先は町である。
こうやって並べると、年を経るに従って寺山の狙いが「町」へと変化していったようにも見えるが、これらは恣意的に抜き出してみたものに過ぎず、本当のところはよく分からない。ただ、町の魅力を見出した寺山がジッドの言葉を次第に自家薬籠中のものとしていく過程で、町は捨てる対象から読む対象になっていった、という仮説をここでは立ててみたい。
ジッドはナタナエルへ、私から離れよ、街を出よ、と諭すが、寺山は「町へ出よう」と誘う。藤本はこれを指して「寺山にあっては勧誘であるからして,読み手だけでなく寺山も町へ出るのだ」と書いている。これもまた、寺山による大きな改変の一つである。「青春煽動業」を自称し、自身の劇団に大勢の家出者をむかえた寺山らしい奪胎といえようか。
寺山は、先に引用した「書物という虚構」において、読書という行為を様々に描写する。
読書は非力な人たちにとっては変身の機会であり、愉悦快楽であり、しばしば武器であり、逃避の場であり、事件であった。
それにもかかわらず、現代人の書物という小道具の使い方は、きわめて画一的であり、生真面目でありすぎる、というのが私の印象だ。
私の母は、子供時代に書物をえらぶとき『面白くて、ためになるもの』をすすめたが、その伝統は今でも多くの書物えらびをする人々の心情に深く根を下ろしていて、『ためにならない』もの、つまり『益しないもの』はなかなか読まれない、というのが実状なのだ。ベストセラーのランキング上位を占めているのはつねに『実用書』または『実用価値をともなったフィクション』である。
私は読書はそれ自体に何の使命も持たぬ(あるいは無駄さ、という効用を持った) 日常行為でありたいと思いつづけてきた。それは、遊びの一種であり、集団読書、ランニング・リーディング、書物のない読書と、限りない可能性の中でたのしまれつつ創造されてゆくべきものであり、バルザックのいう『読書という死の行為』の超克でなければならないのだ。読むことは、それ自体が増殖をはらんだエロス的な行為なのだから。
これらを読むと、寺山の「書を捨てよ、町へ出よう」という煽動の狙いが少し鮮明になってくる。寺山にとって、書物とはそもそも捨てるようなものではなく、日常になくてはならない戯れの対象であった。「書を捨てよ」とは、画一的で生真面目で、実用一辺倒で「ためになる」ような読書をするくらいなら、町へ出て、読書が本来持ちえた「遊び」の感覚を取り戻せ、ということであろう。「読書は非力な人たちにとって…」の一節は、そのまま町にも当てはまる。町は私たちにとって「変身の機会であり、愉悦快楽であり、しばしば武器であり、逃避の場であり、事件であ」るのだ。
読書も町へ出ることも、創造的な「遊びの一種」である、という寺山の境地に私は強く共感する。この意味での「遊び」こそを、自分の生涯の研究対象としたいと、最近は考えるようになってきた。そのことについては、おいおい書いていこうと思う。
ところで、今日出海が訳した新潮文庫版『地の糧』所収の「一九二七年版の序」に誤訳を見つけた。序の最終段で、
或る人々はこの書の中にある、欲望と本能の讃美を見ることができぬ、或いは見ることを承知せぬ。
と、同書が受けてきた誤解について述べた箇所があるのだが、原文ではこのように書かれている。
Certains ne savent voir dans ce livre, ou ne consentent à y voir, qu'une glorification du désir et des instincts.
これは “ne…que” 構文なので、正しくは以下のように訳すべきだろう。
或る人々はこの書の中に、欲望と本能の讃美しか見ることができぬ、或いはそれらしか見ようとせぬ。
念のため、Dorothy Bussy による英訳3を参照してみたが、該当箇所は以下のように訳されている。
Some people can only see in this book—will only see in it—a glorification of desire and instinct.
ジッドは、『地の糧』は欲望と本能の讃美にとどまらない、あるいはそこに重きを置いたものではない、ということをあらためて強調していた。しかし今日出海の訳では逆になってしまっている。
今日出海は同書に寄せた「あとがき」で以下のように述べている。
私は『地の糧』を欲望解放の書だと思っている。カトリック的禁欲の戒律から欲望を解放しようという思想が貫いている。
実際、同書は欲望の解放を煽動する側面を持つのではあるが、ジッドはむしろ、同書がただ欲望解放の書としてのみ読まれることに困惑していたようだ。もっともそれは、20代で書いた『地の糧』から30年を経て老境にさしかかったジッドの、心境の変化も手伝ってのことではあるのだろうが。
ではなぜ今日出海はこのような誤訳をしてしまったのだろうか。「一九二七年版の序」全体を見渡せば、今日出海の訳がおかしいことはすぐに気づく。今日出海も素直に原文を読んでいれば、このような間違いはしなかっただろう。しかし上で引用したように今日出海は同書を「欲望解放の書」と決めつけてしまった。「あとがき」で語るところから計算するに、今日出海が同書を初めて読んだのは1928年頃であり、 1927年版を入手していたかどうかは微妙なところである。もしかしたら、1927年版ではない古い版の方を今日出海は読み、それに強く影響を受けたのではないだろうか。
「あとがき」の最後にはこのように書かれている。
私は過去を回想するのを好まない。ろくでもない思い出が石ころのように落ちているだけだからだ。けれども『地の糧』を訳しながら無器用にその年ごろの情熱を傾けていたことは事実である。その後幾度か版を重ね、書肆を変えて出版したが、一字も改削をしなかった。そのころを懐かしむために。
あるいはもしかしたら、後年この誤訳には気づいていたがあえて直さなかった、ということかもしれない。
-
藤本智成「『地の糧』を読む寺山修司」リュテス Vol. 50,大阪公立大学フランス文学会, pp. 16-30 (2023) ↩︎
-
André Gide. “Fruits of the Earth”, translated by Dorothy Bussy, Secker & Warburg. (1949) ↩︎