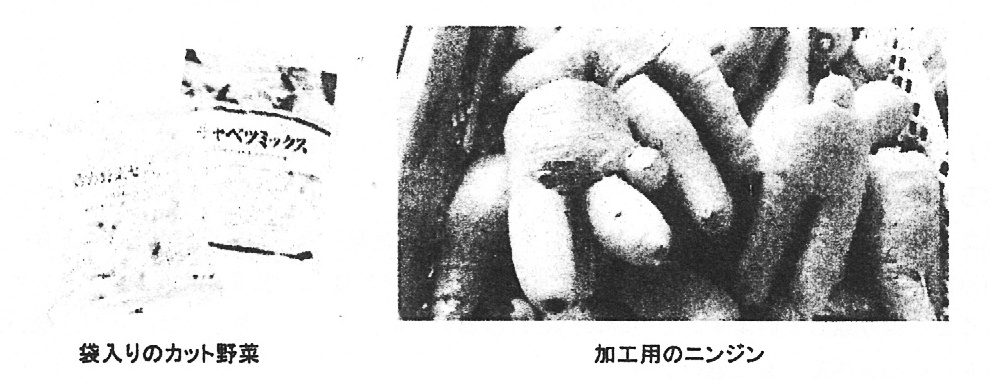「考えさせる問題」への疑問
数年前に、麻布中学の社会のある入試問題が「考えさせる問題」として SNS で話題になった。取り上げられたのは、2021年度の社会の、大問1の問6である。以下にその問題を引用する。
問6 下線部カについて。大型スーパーやコンビニのプライベートブランド商品として、袋入りの便利なカット野菜が増えてきたのはなぜですか。下の写真を参考にして、購入する消費者にとっての理由と、スーパーやコンビニと契約する農家にとっての理由を、それぞれ答えなさい。
なるほど面白い問題の作り方をするものだな、と思う。先に断っておくが、ただ暗記した知識量を問うだけの問題よりかはよほどよい試みであろうことについては疑いを持っていない。麻布の問題はこれに限らず、毎年様々な工夫が凝らされており、新しい問題を見るのを毎年楽しみにもしている。
ただ、これが本当に思考力を問う問題となっているかというと、やや疑問が残る。というのも、この問題はよく考えて解こうとすると、かえって解答が難しくなるように思えるからだ。
加工用野菜の背景
市販の過去問集に付された、この問題の解答例を見てみると以下のように解かれている。
消費者: 必要なだけ購入でき、しかも調理の手間が少なくてすむ。
農家: 細かい規格に合わせる必要がないので、廃棄される野菜が減る。
SNS での反応をざっと眺めても、おおむねこの解答例に沿った考え方をしているように見える。かくいう私も第一感としては同様の答をまずは想像した。
しかし同時に、はてこれはそんな単純な答でよいのだろうかとも思った。気になったのは写真に掲載されている人参で、これをカット加工するのはちょっと手間がかかりそうだなぁ、と思えたのだ。皮を剥くのも簡単ではなさそうだし、一般的な形状の人参をカット加工する機械に、二股にも三股にも分かれているような人参を入れられるのか、よくわからない。さらに、問題文にある「スーパーやコンビニと契約する農家」という記述を読んで、そもそも農家がそうした業者と直接契約するということを知らなかったことにも思い当たった。要するに、この問題についてきちんと考えようとすると、知らないことがいろいろある、ということに気付くのである。
なので、それ以上自力で考えるのはやめて、手のあいたときに調べてみたのだが、すると当初の思いつきとはだいぶ異なる情報を見つけることができた。
まず驚いたのは、カット加工用野菜といえど、実はいろいろと規格がある、ということだった。例えば独立行政法人農畜産業振興機構がまとめた『平成24年度カット野菜需要構造実態調査事業 報告概要』によれば、カット野菜用原料であっても、「不揃いな規格は品質や作業効率が落ちるため、比較的揃った規格を希望する声が多く聞かれた」とある1。また「大型化することによって味が落ちることや、規格が揃わないことによる作業ロスを危惧する意見も多かった」とあり2、カット野菜だからといってどんな野菜でも使える、ということにはならないことが窺える。
同様のことが、野菜流通カット協議会がまとめた『加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン2023』からもわかる3。同資料は野菜生産者と加工業者間での取引契約におけるガイドラインを示したもので、主に業者側が加工用野菜に求める規格例が様々な野菜ごとに記載されている。例えば大根であれば「加工歩留まりの観点から尻詰まりの良い円筒形の形状が求められており、曲がり、岐根(根が枝分かれしたもの)、裂根は敬遠されています」などと説明されている。
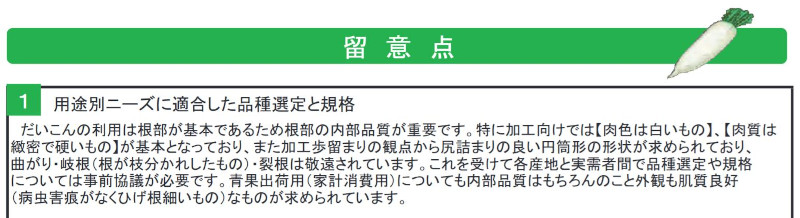
一般社団法人日本施設園芸協会『加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン2023』 p. 29より、加工・業務用だいこんに求められる品質についての説明。
あらためて考えてみれば、省力化を目的とした機械加工では、機械に投入する原材料は、ある程度品質が揃っている方が効率がよいのは当たり前だ。皮を剥いたり大きさを切り揃えたりする手間を考えると、問題に掲載されている写真に写っているような人参は、カット加工用としてはむしろ望ましくない、という可能性もあるだろう。
ではカット加工野菜の出荷量が増えている要因は何だろうか。その一つとして、農家側の省力化が挙げられる。農林水産省がまとめた資料によれば、加工用野菜を作る利点に、選別が不要となり、機械を用いて収穫作業を省力化できることが第一に挙げられている4。同資料ではさらに流通コストの低減もその利点として挙げられており、生産から流通・加工まで含めての省力化が、その主要な利点と考えられていることが見てとれる。

農林水産省『野菜をめぐる情勢(令和7年4月)』p. 21 より。
もちろん、上掲資料や農林水産省の他のページなどにもあるように、野菜の廃棄を減らしたいという関係者の熱意もあってのことだろうが、日本全体で野菜の消費量の減少が続いている5中で加工用野菜の出荷量が増えている6理由の一端はこのあたりにあると考えるのがひとまずの解答となるだろう。
この問題はさらに深く掘り下げて考えることもできそうだが7、ひとまずこのあたりで切り上げ、本題に入ろう。
「考えさせる問題」は人々を考えさせたのか
断っておくが、麻布のこの問題は、わずかに瑕疵はあれど、基本的な構造は中学入試問題として不適切であるとは思わないし、引用した解答例が間違っているというつもりもない。小学六年生に求められる解答としては妥当なところだろう。
では私は何に引っかかっているのか。
この問題は上に述べたような様々な事情が絡んでいるのだが、そうした事情に思い当たった受験生ほど、かえって解答に困ってしまったのではないだろうか。私と同じように問題中の写真を見て疑問を感じた者もいただろうし、たとえば親がスーパーに勤めていてカット加工の話を聞いたことがあったり、家業が農家で出荷作業を手伝ったことがあったりするなどして、上で私が調べたようなことの一端をすでに知っていた者もいたかもしれない。小学校の総合学習の時間で、SDGs 絡みでフードロスについて意欲的に調べた経験のある小学生も、いまどきであれば少なくないだろう。そうした知識のある学生にとっては、この問題について真剣に考えた上で 20〜30字程度の解答欄に収まるような答を制限時間内に書くのは、簡単なことではないだろう。
要するに、こうした問題は、真剣に考えてしまうとかえって解答が困難になることがあるのだ。
しかしそれでは効率的に受験対策を進められない。そこで求められる対策は簡単だ。考えないことである。そして多くの人が、この対策に慣れ親しんでいるように私には思える。
先の麻布の問題であれば、結構な割合の人が、問題を見て瞬時に、規格外野菜の活用というとりあえずの解答に辿り着くだろう。そして SNS での反応を見る限りでは、「考えさせる問題」としてこの問題を称揚した人でも、それ以上のことを考えない、という選択をしたようだ。
ここで、そういうお前もたいして考えずに、ネットで調べものをしただけじゃないか、という反論も出てくるかもしれない。事実、前節まではあくまでも調査結果を示しただけにとどまっており、その先の考察までは書いていない。
しかし、こうした調べものも「考える」ことの一部なんだ、ということを、ここであらためて強調しておきたい。問題を前にして腕を組んでウンウン唸るのは、「考える」という行為のほんの一部にしか過ぎないのである。
そして、どうもその「考える」ということについて、十分な訓練を積む機会が学生には足りていないのではないかと、大学での指導を通じて思うことがある。その原因の一端が、ここまで議論してきたような、いっけん「考えさせる問題」に対する「考えない」という対策に、少なくない数の学生が慣らされてしまっていることにあるのではないか、というのが私の懸念なのである。
「考える」訓練
考える訓練が足りていないのではないか、と思うのは次のような状況を見かけたときである。例えば講義でのレポート課題やグループワーク、あるいは卒業研究などの場面で、なにか困難な課題に取り組もうとするとき、たいていの学生はまず直接的な答を探そうとして検索エンジンや生成AIに頼るのだが、それで答が見つからないと感じたら、少なくない数の学生が、あっさりと諦めて解答を放棄するか、机の前に座したまま、手を動かすことなく頭の中で考えて答を捻り出そうとするのである。
解答を放棄してしまう方の学生についてはここでは置くとして、まがりなりにも頭を働かせて答を導こうとする方の学生について、どうしてその意欲がありながら、頭だけでなく手を動かそうとしないのか、それが以前から不思議でならなかったのだ。
哲学者の野矢茂樹が「考える」とはどういう行いなのかを説いた著作『はじめて考えるときのように』で、次のようなことを述べている。
「頭の中で考える」という言い方がふつうにされてしまうことには、「考える」ということに対する誤解があるかもしれない。筆算じゃなくて暗算でやった方が「考える」という感じがする。紙の上で機械的に計算をしているだけだと、「考えてる」とは言ってもらえないけど、「ちょっと待ってね」とかいって「うーん」なんて暗算して答えを出すと、「考えた」と言ってもらえそうだ。
これと同種の誤解を、私が気にしている、机の前に座して答を捻り出そうとしていた学生達も抱えているように思える。
では、本来の「考える」という行いはどのようなものなのか。上記の引用箇所より少し前の頁で、野矢は以下のように述べている。
どうも気になるのは、「自分の頭で考える」という言い方だ。よくそんな言い方を聞く。それがだいじだとか、いまの若いひとは自分の頭で考えようとしないとかも言われる。だけど、ぼくの考えでは、これはふたつの点で正しくない。
考えるということは、実は頭とか脳でやることじゃない。手で考えたり、紙の上で考えたり、冷蔵庫の中身を手にもって考えたりする。これがひとつ。
それから、自分ひとりで考えるのでもない。たとえ自分ひとりでなんとかやっているときでも、そこには多くのひとたちの声や、声にならないことばや、ことばにならない力が働いている。じっさい、考えることにとってものすごくだいじなことが、ひととの出会いにある。
そう、「考える」ということは本来、一人で、頭の中だけで行えることではないのだ。本を読むのも調べものをするのも、それらはつまり過去の誰かの頭を借りて、一緒に考えることに他ならない。また、手を動かして、それまで調べたことをメモとして書き出し、それらを並べ替えたり削ったりして、紙や画面の上で、整理していく、そうしたことをも含めて「考える」と呼ぶ。机の前でウンウン唸るのは、考えるやり方としてはむしろ効率が悪い。
冒頭で紹介した入試問題も、私がそれまでに持っていた知識だけで考えると、「規格外野菜の活用」程度の、ごく浅い考察までしかできなかった。いろいろと調べてようやく、この問題についてよりよく考えるための下準備が整ったのだった。
だとするならば、だ。制約だらけの試験会場で「考えさせる問題」に取り組ませることは、本当に「考えさせる」ことになっているのだろうか。ややもするとこの種の問題は結局、どこかで習ったり見かけたりした答っぽいものを知っているかどうかを問う問題になってしまうのではないか。
これは、教育機関に身を置き、学生に試験をさせる側である私にとって非常に重い問題である。多くの試験問題が暗記力偏重だの計算力偏重だのと批判を受ける中で、工夫を凝らして編み出された「考えさせる問題」でさえも、かえって考えない習慣に結びついてしまうのだとしたら、どうすればよいのか。
この課題に対して、「考えさせる問題」の新しい形式が作れないかと、ここ数年ほど試みていることがある。自分の中ではなかなかうまくいっているように見える部分もあり、手応えを感じている。ただ、最近になってこの試みの前にあらたな障害が現われてしまい、対応に苦慮もしている。問題を作るというのはやはり一筋縄ではいかない、難しいことであるということを実感している。
これについては稿をあらためて論じることにしたい。
練習問題
さて、その「新しい形式」のことはともかくとして、ここまでの私の主張に一理あると思っていただけた方向けに、いっけん「考えさせる問題」であるかのような練習問題を作ってみた。もともと「考えさせる問題」としてどこだったかで紹介されていたのを、本稿での主張にあわせて改作したものである。
LED はその効率の良さから、ディスプレイ用素子として期待が高かったのですが、赤色の LED は比較的早い時期に明るくて効率のよいものができた一方で、青色や緑色の LED は明るくて効率のよいものがなかなかできませんでした。しかし赤﨑勇や天野浩、中村修二らの研究により1990年代に明るい青色 LED が実用化され、ついで緑色 LED も実用化に成功し、現在では LED ディスプレイの他、電球や蛍光灯に代わる省エネルギーの照明として広く使われています。
問題: 照明用の白色 LED で広く用いられているものは、どのような原理で白い色を発していると思うか。簡潔に記せ。
いかがだろう。すぐに解答は思い浮かぶだろうか。
この例題には、気にかけて欲しい箇所が二つある。まず、この問題に対する解答を、おそらくは多くの人が間違える。本稿で述べた意味において、よく考えてみて欲しい。
そしてもう一つ、問題文を読んで「あれ?」と思う方も少くないだろう。一般に知られる LED の開発史とは少し説明が異なるからだ。もし、問題文がおかしいと思ったら、ぜひ手を動かして調べてみて欲しい。
この問題の解説は、別記事に記すつもりだ8。
-
独立行政法人農畜産業振興機構『平成24年度カット野菜需要構造実態調査事業 報告概要』p. 6 ↩︎
-
同 p. 24 ↩︎
-
一般社団法人日本施設園芸協会「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン2023」(農林水産省 / 加工・業務用野菜対策のページから取得) ↩︎
-
農林水産省「野菜をめぐる情勢(令和7年4月)」p. 21(農林水産省 / 野菜のページから取得) ↩︎
-
同 p. 24 ↩︎
-
同 p. 2 ↩︎
-
例えば、家計消費用の生鮮野菜と比べて、加工用野菜の場合は輸入品との価格競争が問題となる。カット野菜類の需要が増え続けていくと、農家にとってはかえって厳しい状況を招くおそれもあるだろう。
問題文の「大型スーパーやコンビニのプライベートブランド商品として」という記述にも注目したい。スーパーの売り場には、カット野菜製品はプライベートブランド商品に限らず、様々な業者のものが並んでいる。もしこの問題が大学生以上に向けて出題されたものであれば、プライベートブランド特有の事情を考慮した解答が求められるだろう。農家から見て、カット野菜製品の加工業者との契約とスーパーとの契約とで、どのような違いがあるのかも調べる必要がありそうだ。 ↩︎
-
解説を次の記事に記した: 「『考えさせる問題』への疑問」に掲載した練習問題の解説 (2025.10.11) ↩︎