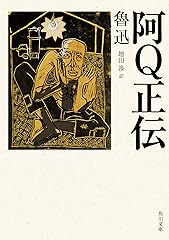小人朝に不善をなし、夕に之を繕う
もう十年以上前のことだが、新宿駅で体験したごく私的で些細な出来事について書いてみようと思う。
朝の出勤時、いつものように新宿駅構内を、中央線のホームへと向かって早足で歩いていたのだが、前を歩いていた女性が私の進路を横切ろうとした。そのとき、彼女が引いていたキャリーバッグにポンと私の足が当たってしまい、バッグを軽く蹴り上げたような格好になってしまった。急な進路変更だったとはいえ、私がバッグへと追突した格好であるのだから、悪いのは私である。ただ、いまではその理由も思い出せないが私はその日やや苛立っていて、おそらくその感情が顔に出てしまっていたのだろう、私の方を振り返った女性も、一拍遅れて嫌悪の表情へと変わっていった。一言謝るべきか、ちょっと逡巡する間に女性は去っていってしまった。
その日は一日、そのことが心に引っかかっていた。指先にトゲが刺さったときのような、痛がったり絆創膏を貼ったりするような痛みではないがふとしたタイミングで気になってしまう、そんな感じの痛みだ。その女性に対して申し訳なかった、ということ以上に、しょうもない理由で逡巡し、謝る機会を自ら逸してしまったことへの恥ずかしさと後悔をずっと引きずってしまった。
夕方、帰路ふたたび新宿駅にて、たしか東急ハンズだかなんだったかに用事があって、中央線のホームから南口へと向かった。当時はあのホーム端の階段にエスカレーターはなかったように思う。その階段の上の方から、見るからに重そうなスーツケースを持って、一段々々、あぶなっかしい手つきで降りてくる女性がいた。もちろん、朝のキャリーバッグの女性とは別人である。そこまで出来過ぎた話ではない。ともあれ私は即座にその女性に声をかけ、スーツケースを運ぶ手伝いを申し出たのだった。
それで朝の女性に対して罪滅ぼしができたというつもりはない。ただ、少なくとも私は少し気が晴れたし、そんな機会がその日のうちに巡ってきたことを、スーツケースを運びながら私はありがたく思ったのだった。
「小さな事件」は、人力車に乗っていた「私」が遭遇した交通事故の話だ。「私」が乗っていた人力車に老婆が接触し、倒れてしまう。「私」は、たいした怪我でもなさそうだから車を出せと指示するのだが、車夫は老婆を伴って近くの派出所へ向かう。その姿を見た「私」は、自分の卑小さに思い至る。
魯迅は最後にこう書いている。
このことは現在になっても、まだ時々思い出す。私はそのために時々苦痛にたえられず、努力して私自身について考えてみようとする。数年来の国家の政治向きのことは、私にはもう子供のとき読んだ「子曰く、詩に言う」(中国の古典をさす)と同じように、半句も暗じることができない。ただこの一つの小さな事件だけは、どうしても私の眼の前に浮び、時として一きわハッキリした形になって、私を羞じ入らせ、私に自分を改めるよう催促し、そして勇気と希望を増してくれる。(増田渉訳)
これを読んで、そういえば私にも自分を見つめ直させるような記憶があったことを思い出したのだ。
私には他にも、魯迅同様、思い出すだけで恥ずかしくなってしまうような、自分の卑小さを思い出させてくれ、態度を改めよと催促してくるような思い出はいくらでもあるのだが、しかしこの新宿駅での出来事は、それらとは異なる後味を持つ。
「小さな事件」は、そんな「世界をまのあたりに」しようとした魯迅の静かな覚悟が表われているように思う。
現代の我々にとって人の世に生きることが事実上唯一の選択肢である。その住みにくさ故に、嫌な目にも会うし、人を嫌な目に会わせてしまい、それによって自分の卑小さを思い知らされることも度々ではあるのだが、人の世に生きることで、誰かのためになることもできる。日々傷つきそれを癒す、生きることはその繰り返しなのだろう。その度に、少しずつ私は変わっていく。
身近な「小さな事件」は、薄暗き世にあって私が依って立つ地点に目を向けさせるべく、足元を静かに照らす街灯のようなものに感じられる。