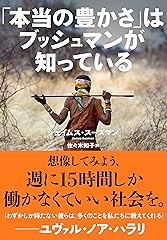一之輔の「あくび指南」を聞いて泣きそうになった話
少し前にとある落語会で、春風亭一之輔による「あくび指南」を聞く機会があった。
噺に入る前のまくらとして、一之輔は昔の職人事情について語った。なんでも昔の職人は、腕の立つ者や、あるいは逆に不真面目な者は、早い時間にとっとと仕事をたたんでしまい、遊びに出かける奴等も少なくなかったそうで、そうした連中の遊びの一つが義太夫やら長唄やらの稽古ごとだったという。
一之輔の「あくび指南」は、そんな職人である八五郎が町をぶらついていると、あろうことかあくびの仕方を指南するという看板を見つけ、なんじゃそりゃ、と思いつつも、その近くを掃き清めていた美女を師匠と勘違いしてしまい、あくびの稽古をつけてもらおうとするところから始まる。もちろん、本当の師匠が奥から出てきて、八五郎は「しまった」と思うも今さら勘違いとも言い出せず、あくびの稽古をつけてもらうことになる。
ところが、この師匠が教えようというあくびは単に大口を開けて「あーあ」と言うようなものではなく、春夏秋冬、季節に応じてシチュエーションを想定し、それにふさわしいあくびを演じようというものだった。例えば「夏のあくび」であれば隅田川に小舟を出して舟遊びをしていたものの、退屈になってきて思わずあくびが漏れ出る様を、芝居のようにセリフつきで演じるのである。八五郎は「思ってたのと違う!」と興奮し、前のめりであくびに取り組む。
さて、その日一之輔が演じた師匠のあくびが実に見事なもので、聴いているこっちも「思ってたのと違う!」と興奮してしまうほどだった。 YouTube にも一之輔の「あくび指南」がアップロードされていたので、ぜひそちらでご確認いただきたい。(なお、私見では先述の落語会のときの方がずっと見事だったように思う)
そんな訳で、落語としてはおおいに楽しめたのではあるが、その一方で聞いているうちに無性に悲しくなってしまい、ギャグ満載の一之輔版「あくび指南」であるにも関わらず、噺の途中で思わず泣き出しそうになってしまった。
きっかけは、舞台上で一之輔が演じるあくびの師匠が稽古をつけているとき、一之輔を通じて実は観客の我々も、あくびの稽古をつけてもらっているも同然である、ということに気付いた時である。
現実の観客席で噺を聞いている我々も、作中の登場人物と同じ立場で、あくびの指南というこの上なく馬鹿馬鹿しい稽古ごとを楽しんでいる。それこそがこの上なくゆったりとした、贅沢な時間であるように思えた。と同時に、そんな暇を我々が持てるのは年に数えるほどしかないのに、作中の職人は毎日のようにこうした時間を楽しんでいる、ということに思い当たり、なんというかもう、本当に悲しくなってしまったのである。
なんで江戸時代の職人がゆとりに溢れているのに、現代の私はあくせく働いているのか。舞台の上で一之輔演じる八五郎があくびの稽古に興じれば興じるほど、私はその違いに呆然としてしまったのだ。
さて、実際のところ、江戸時代の職人の労働環境はどのようなものだったのだろうか。調べてみたものの、あまりまとまった資料が見当たらない。ネットを検索すると色々な情報が見つかるものの、信憑性に乏しいものばかりで実態はよくわからない。ちなみに「あくび指南」の主人公である八五郎は大工である。腕のよい大工は賃金も高く、比較的恵まれた労働環境にあったらしいことはあちこちに書かれているが、これも具体的なことはよくわからなかった。とはいえ、大工が当時の花形職業であったことは確かで、落語にも様々な大工が登場し、派手に遊びを楽しんでいる描写も少なくないことから、話半分だとしても、腕のよい大工であればそれなりの余裕はあったのだろう。
こうした説には批判も多くて、高い乳児死亡率や短い寿命、生活環境の不安定さを指摘する研究も少なくない3のだが、こと労働時間に関しては、農耕社会によって田畑の整備や収穫物の保存、定住化に伴う諸々の管理業務など、総労働時間を増やす方向に力が働いたのは確かなようである。
同種のことは産業革命やIT革命など、人類史における様々な労働環境の変革期においても繰り返されているようで、生産性の向上は労働時間の短縮を必ずしも意味しない。少なくとも、ケインズが予言したような、技術革新や社会形態の変化による労働時間の短縮は、いまのところ起きる気配はなく、それどころかますます労働時間は増え続けているように思われる。
デヴィッド・グレーバーは著書『ブルシット・ジョブ』で、現代の我々は誰も必要としていないどうでもいい仕事(「ブルシット・ジョブ」)のためにいたずらに労働時間を増やしている、と指摘している。組織管理や説明責任の名のもと、管理やいざというときの言い訳のためだけの、誰も読みもしないような書類作成にみな時間をとられており、そしてその書類を管理するというさらに無駄な仕事に人を従事させる、という地獄のような状況をグレーバーは、彼のもとに世界中から寄せられた様々なブルシット・ジョブについての情報をもとに活写している。
「ブルシット・ジョブ」の言葉が世に送り出されるきっけとなった記事で、グレーバーは以下のように述べている4。
以前、イギリスの大学の学部で、際限のないようにみえる管理責任の増大をまざまざと目の当たりにしたとき、ひとつの地獄の可能性がかいま見えた気がした。その地獄とは、自身の時間のほとんどを、好きなわけでもこれといって得意でもない仕事に投入している諸個人の集合体である。(酒井ほか訳)
私も大学で働く者として、この状況をとてもよく理解できる。誰が望んでいるのかよくわからない仕事がどこからか降ってくる。それがいかにもなブルシット・ジョブのように見えるので文句を言ってみるものの、文句を言われた方もこれまた別の誰かから依頼されて仕方なくやっているのがわかってしまうので、あまり強いことも言えなくなる。グレーバーは先の記事で「まるで何者かが、わたしたちすべてを働かせつづけるためだけに、無意味な仕事を世の中にでっちあげているかのようなのだ」(酒井ほか訳)とまで言っている。
どうせ無意味なことをやらされるのであれば、私もあくびの稽古でもしていたいし、あるいは私もなにか一見無意味だが、突き詰めれば意外に奥の深いあそびを指南する仕事でもやっていたいものである。それとも、無意味な書類書きも、突き詰めるとまた別種の奥深さが現れるのだろうか。5
-
Marshall Sahlins. “Stone Age Economics”, Routledge (2017) ↩︎
-
例えば David Kaplan. “The Darker Side of the “Original Affluent Society””, Journal of Anthropological Research Vol. 56, No. 3 (Autumn, 2000), pp. 301-324 ↩︎
-
David Graeber. “On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant” Strike! Magazine, Issue 3, 2013 ↩︎
-
『だんご3兄弟』や『ピタゴラスイッチ』で有名な佐藤雅彦は、打ち合わせ用に作った書類の出来を褒められたことが、表現の仕事へと踏み出すきっかけだったと明かしている (佐藤雅彦『毎月新聞』毎日新聞社 2003, p. 69 (amazon))。電通に入社したての頃の佐藤はこれといってクリエイティブな仕事に従事していなかったのだが、ある打ち合わせ用に彼が作ったスケジュール表と見積書が、当時まだ学生だった、後にメディアアーティストとなる藤幡正樹に「美しいです」と褒められたという。仕事のための書類を「美しい」かどうかで判断することができる、ということに佐藤は驚いたそうだ。
どんな仕事にもやり甲斐を見出すことはできる、とまとめてしまうと、奴隷の鎖自慢のようにもなりかねない危うさもあるのではあるが、何を「ブルシット」とするかを決めるのは自分である、ということは心に留めおきたい。 ↩︎