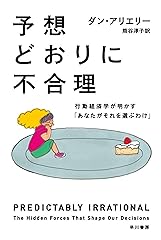乗り遅れたっていいじゃないか
巷に溢れる各種新規サービスについては「本当に善いものなら一年くらい乗り遅れても困らない。もし一年遅れたくらいで損失を被るようなら、それは本当に善いものではない」という信念を獲得して以来、まあまあ心穏かに過ごせるようになった。
断わっておくけど、もう新しいものに飛びつかなくなった訳ではない。例えば Oculus Rift は DK1 から持ってるし、Kickstarter 等のクラウドファンディングでお金を払ったもののあっという間に動かなくなって押入の肥やしになったものは沢山ある。元手のかからないフリーミアムサービスについては言うに及ばず。
一方で、アレだとかソレだとか、世間を騒がしたもののその後あっという間に話題に上らなくなったものについては、上記の信念のお陰で手を出さずに済んだ。要は、飛びつくものの数を絞れるようになった、ということが言いたいだけである。
ある新規サービスについての評判をあちこちで耳にするようになった時に、「今すぐアカウント作って参加した方がいいのか?」と考えることはもちろんいまだにある。その気持ちが、「こりゃ面白そうだ、早く遊びてぇ!」という湧き上がる思いに支えられているのであればそのまま突進すればいいんだけど、もしそれが「今すぐ参加しないと先行者利益にあずかれないのでは?」という焦りから生まれている場合には、グッとこらえて評判が確定するのを待つ方がいい。いちはやく参加した人にのみ利益があるようなシステムは、本質的に善であるとは思えない。ネズミ講とかマルチ商法と同類のように思える。
例えば、最初のインターネットブームの頃、「ドメイン名」は先行者利益が大であると考えられていたシステムだった。「アルファベット数文字 + .com」とか「みんなが知っている英単語 + .com」みたいなドメイン名を抑えたものが勝利する、と多くの人が思っていた。
しかし今ではドメイン名の価値はそこまでではない。TLD も増えたし、そもそもみんな検索エンジンを使って見つけたり、SNS 経由で訪れたり、モバイルアプリから直接アクセスしたりしている。後から参入した組織や個人が十分に利益を享受できるシステムへと改善された。
同様のことは、アカウント名についても言える。例えば「名前 + @gmail.com」みたいなアカウントを取れるかどうか、みたいな争いが新規サービスが立ち上がる度に起きていた訳だが、最近ではアカウント名がそもそも付与されず、メールアドレスがその役割を果す場合が多い。これもまた、先行者利益を必要以上に膨らませない、善いシステムへと向かってネットサービス全体が進歩している表れと言っていいと思う。
もっとも、先行者利益が存在するシステムのすべてが善でないと言うつもりはない。研究開発の分野では先行者利益が競争を促し、それが進歩を加速し、まわり巡って人類全体の利益につながる(持続性を維持しうる限りにおいては)。しかし、先行者利益によって一般ユーザー間の競争を誘導するというのは、私にはあまりいいものには思えない。
これら一連の指針は、行動経済学に関するダン・アリエリーの著書『予想どおりに不合理』に負うところが大きい。人間、どんな条件で目先の利益に目が眩みやすいのか、どうすればそれに立ち向かえるかについて、様々な研究成果を踏まえて詳細に議論されている。強くお薦めする。
そのうちこういった話を、「最近○○が面白くなくなってきた」という古参メンバーの典型的反応や、それが長じて老害が新規ファン参入の障壁になるパターンと絡めて考えてみたい。